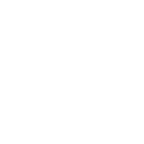トラックのシートに座ったまま、CIDPのことを初めてインターネット検索したとき、スコットさんは頭の中がいろいろな思いでいっぱいになったといいます。この聞いたこともない病気の説明を読み進めていくうちに、恐怖感に打ちのめされていきました。2年間診察を受けていた神経科医から、人生を一変させるような診断を下された、病院の帰り道のことです。これからの、慢性疾患を抱えての人生、これまでとはまったく違う人生……それを思うと、自然に涙が頬を伝います。
ダンサー兼振付師として活躍していたスコットさんが最初に症状に気付いたのは、2013年にショーのオーディションをしていたときでした。ハードワークには慣れているはずが、それまで経験したことのないちくちくとした痛みを足に感じました。そのときは「自分にプレッシャーをかけすぎたかな。そのうち消えるだろう」と思ったそうです。
スコットさんはショーに出演して踊り、演出し、振り付けをしながら足に負荷をかけ続けました。痛みが自然に消えることはなく、以前受けた人工股関節置換手術の合併症を心配したスコットさんは、かかりつけの外科医に相談しましたが、「ちくちくした痛みは手術には関係がないので安心するように。神経科医を受診してはどうか」と助言を受けました。
スコットさんは2人の神経科医の診察を受けましたが、どちらもCIDPにはまったく詳しくありませんでした。
「CIDPは希少な疾患で、存在すら認識されていませんでした」。
3人めの神経科医でようやくCIDPと診断されましたが、治療やサポートは難しく、スコットさんは治療を受けられる施設を探しました。
CIDPを検索して受けた衝撃から立ち直ったスコットさんは、パートナーのアベルさんと一緒にCIDPについてできる限りの情報を集めました。
その結果、幸いにも自宅から最寄りのCIDP中核拠点であるGBS | CIDP Foundation Internationalにたどり着くことができました。
現在では、医療サポートチームがスコットさんを支えています。
「5人のチームがこの8年、サポートしてくれています。ありがたいことです」
CIDP中核拠点は、教育や支援を提供しています。
自分に言いました。病気から身を隠すことはできない。
自分の一部にするだけだと。
スコットさんにとってのターニングポイントは、「前に進むには診断を受け入れなければならない」と気付いたときでした。
「私は長い間、CIDPに怯えていました」
スコットさんは当時を振り返ります。
「でもある日、自分に言いました。病気から身を隠すことはできない。自分自身の一部にするだけだと」
「『これも自分の一部。これが今の自分の人生の一部。この事実と向き合わなければならない。これを乗り越えて成長するんだ』。一度そう言えたから、おかげで今があります」
スコットさんにとって“CIDPを受け入れる”ということは、自分が深刻な病気であることをただ認めるだけではなく、人生をもっと楽に生きる方法を受け入れること、そして自分に手を差し伸べてくれる親しい人たちの申し出を受け入れることも意味していました。
「クオリティ・オブ・ライフを改善するものでありながら、自分自身で遠ざけていたものがたくさんありました。車椅子や障がい者マークを使おうと思えば、いつでも使えていたのに」
スコットさんはCIDPを受け入れるだけでなく、CIDPと寄り添う人生を送るために、3つのことを決めました。
- まずは治療。医師の話に耳を傾け、受診予約は必ず守る。
- 医療サポートチームや家族、友人とよい関係性を築き、保つ。
- CIDPと診断された心の負担に向き合う。
「この先、物事がこれまでと違うことがあっても、一日一日をどう生きていくのか、学び続けなければいけないのです」
介護者には細かく伝える必要があります。
でなければ介護者は助けようがないので。
友人や家族の支えも、スコットさんが日常生活で前に進む助けになっています。「友人や家族は、私の心の揺れ動きを一緒に経験してくれています。感謝の言葉を伝えるのを忘れないようにしなければ」
と同時に、スコットさんはパートナーであり介護者であるアベルさんとの意思疎通の大切さを実感しています。日々の体調を相手にきちんと伝えるのです。「CIDPは毎日状況が変わります。朝、目が覚めて、強い気持ちでいられる日もあれば、目覚めてもベッドから出られない日もあります。介護者には細かく伝える必要があります。でなければ介護者は助けようがないので。今の自分の状況を理解してもらうことが大切です。そうすればその日1日、手を貸してもらえます。支えてくれる人たちを驚かせたくないですからね」
どんな情熱を持っていたとしても、それを果たせないかもしれません。
ですが、自分を変えることはできます。
スコットさんの願いは、いつか演出家やプロデューサーとして再び劇場に戻ること。そのためには別の表現手段を身につけなければならないと考えています。「毎日がニューノーマル。すべてはメリーゴーランドのように、あっという間に一回りし、降りられなくなります。自分自身を変えなければと感じています」
この悪戦苦闘の中でスコットさんは強いひらめきを得ました。「僕の頭を殴ったのが神か宇宙かはわかりませんが、『作家になれ』と言われたように思いました」
劇場は、ダンスや演技を通じて物語を伝える一つの手段でしかないと気付いたそうです。誰かに伝えたいアイデアや物語を形にするために、物を書くという別の機会を得ました。
「以前から物を書きたいとは思っていました。紙やノートにアイデアを書きためていました」
執筆を始めるにあたって調査をしたり、学術書を読み、現在は作家への道を着実に歩んでいます。
新しい情熱を探しているCIDP仲間へのスコットさんからのアドバイスです。
「どんな情熱を持っていたとしても、それを果たせないかもしれません。ですが、自分を変えることはできます。私は自分自身を変え、そこに情熱を注いでいます」